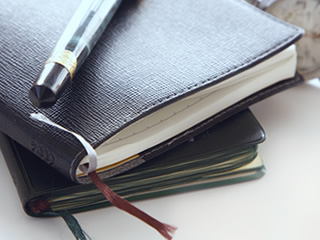|
2019/10/3
|
|
非正規公務員について |
|
|
1.10.1付けの毎日新聞の記事に「非正規地方公務員 急増」の記事が載っていました。新聞によると、総務省の調査{2016年)で全国で約64万3千人と、この11年で4割増加しているそうです。正規職員の定数増やせないことや業務の多様化が背景にある。最大の問題点は低賃金で、正規の3分の1と言われています。 来年4月の地方自治法の改正の施行に伴い、期末手当の支給で改善も見込まれますが、逆に一部の自治体では、賃金そのものを下げたり、フルタイムからパート化で改正法逃れのようなことがおきていることもあるようです。 その新聞の紹介されている30代の家庭児童相談員の男性は管内の100のケースを抱え、面談や報告書作りに忙しい日々。週4日手取り月18万円とのこと。それだけでは、暮らせないのでスクールカウンセラーなどトリプルワークでなんとか暮らせていけるとのこと。 いま話題となっている子の虐待などの相談窓口である相談員の体制が、非正規職員でなんとかやっている現状で本当によいのか疑問です。 いま「働き方改革」で、「同一労働同一賃金」で正職員と非正規職員の待遇の不合理な差を設けることが禁止され、差があれば、どのようなことで差があるのか説明することが求められます。パートタイム・有期雇用の改正で大企業は、2020年4月、中小企業は2021年4月から施行されます。 民間企業では、これに向けて説明できるよう、基本給や手当などの格差の見直しなどを進めているところです。 国家公務員や地方公務員は、労働基準法などの法律は適用除外となっていますが、それらの法律を守らなくてならないと思います。 国や地方自治体は、法律を守もらなければならない義務があるからです。 この前も、ハローワークの職員が、非正規職員が増加していると聞きました。職を紹介しているのが、非正規の職員であるとはどうなんでしょうか。 実は私も、現在地方公務員で、再任用で正職員の半分の勤務で働きながら、社労士事務所もやっています。 この新聞記事には、関心があり、興味深いものです。社労士としても「働き方改革」でいろいろアドバイスする立場もあり、これからも注意深く見ていきたいと考えます。 |
|
| |