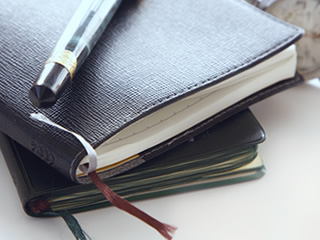|
2019/9/17
|
|
パワハラについて |
|
|
前回のブログでパワハラの法制化についてお話ししましたが、今回はその続きです。 ここでちょっといい話。 ある年配の夫は、奥さんが寝たきりの状態で、24時間の介護をしていました。本人の唯一の楽しみは1週間に1度の買い出しと奥さんには悪いと思いますが、コーヒーショップでの息抜きで、30分程度好きな本を読みながら過ごし、また介護に戻っていくというものです。 その後、奥さんも他界し、一段落した頃、久しぶりにそのコーヒーショップに行きました。そこでいつものミルクティーのミルク多めをたのもうと店員さんを呼び止めたところ、「いつものミルクティーのミルク多めでいいですか。」と私の好みまでわかっています。そう何回も来ていませんが、私の好みまで解っていたのです。また、あるときには「今日もいつもでいいですか」「いやおなかの調子が悪いのでミルクなしの紅茶で」と注文したら、その後いったときも「おなかの調子はのりましたか。おなかに優しいものにしましょうか」と聞いてくれます。そして対応してくれなかった従業員さんからも、「おなかの調子は直りましたか。」と声をかけてくれます。お客さんの情報を共有しているのです。 なかなかの気配りのできる従業員さんばかりと感心します。従業員も大部分が学生アルバイトです。店長に「教育の行き届いた職場ですね。どのようなことをしているのですか。」と訪ねたら、店長曰く「なにもしていません。ここで働くことが楽しいと思えることが大切で、自分たちが楽しくなければ、お客さんを楽しませれません。私たちがいい環境で働いていることが、お客さんにいいサービスができると思いますよ。」 この店長は、日頃から従業員の悩み相談をしていたり、テストの時は早めに上がらせていたりします。 このような職場は、働いていて楽しいのでしょう。そのような職場でなくてはなりません。 このような職場では、パワハラがないでしょう。 パワハラのおきている職場は、まわりにも伝染していて、暗くていやなものです。言われている本人も、そのまわりにいる人もいい気持ちはしません。 研修等でパワハラ対策を行い、気持ちのよい環境にすることが求められています。 |
|
| |